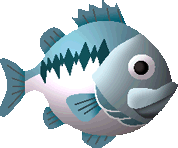
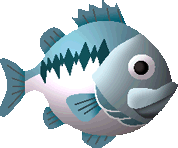
| 魚名 | 種類 | 説明 |
| アカザ | コイ目ギギ科 | |
| ウグイ | コイ目コイ科 | 木曽ではアカウオとよんでいる |
| アブラハヤ | コイ目コイ科 | ウグイに比較して味は悪い |
| カマツカ | コイ目コイ科 | ドウゼンとかスナモグリともいう |
| ニゴイ | コイ目コイ科 | カワゴイともいう |
| オイカワ | コイ目コイ科 | 関東地方ではヤマベ,関西ではハエと呼ぶ。この地方では雄はオイカワ、アカモト、アカダ、アカヒレ雌と幼魚をシラハエともいう。 |
| カワムシ | コイ目コイ科 | 体は側扁し,頭部は比較的ずんぐりしており,口ひげがない。日本に最も普通の淡水魚で,形,色彩などに変異が多く,キンブナ,ギンブナなどに区別される。 |
| コイ | コイ目コイ科 | 養殖の物が野生化した。 |
| フナ | コイ目コイ科 | |
| イワナ | ニシン目サケ亜目サケ科 | 冷水系を好む。警戒心が強い。 |
| カワマス | ニシン目サケ亜目サケ科 | 原産はカナダ、北アメリカで日本には1901年に移植された。 |
| アマゴ | ニシン目サケ亜目サケ科 | タナビラ、アメノウオ、アメなどという。 |
| ドジョウ | コイ目ドジョウ科 | 全長10〜18cmで,一般に雄は雌より小型である。体は細長く円筒形でやや側扁する。口は下面についており,そのまわりに10本のひげがある。鱗はきわめて小さい円鱗。側線は体の中央にまっすぐに走っている。一般に雄は雌より鰭が大きく,特に雄の胸鰭の第2軟条は雌に比べて大きい。体色は暗緑色で不規則な暗色斑があり,腹面は白い。淡水の泥底にすみ,泥中にもぐるが,ときどき水面に出て腸で空気呼吸もする。 |
| シマドジョウ | コイ目ドジョウ科 | カワドジョウ、ムギナ、ムイカラドジョウ、ムイカラ、カンナメドジョウなどという。 |
| アジメドジョウ | コイ目ドジョウ科 | 丹羽彌により発見された。 |
| カジカ | カジカ目カジカ科 | ウタウタザッコ、オタフクザッコ、カブッチ、カブなどという |
| ヨシノボリ | スズキ目ハゼ科 | オオクマザッコ、スイツキ、ドウゼン、ヒデリカジカなどともいう。 |
| アユ | ニシン目サケ亜目アユ科 | 養殖の稚魚を放流した物が多い。 |